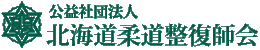| 生 年 月 日 | 昭和48年5月10日 | 開業年月日 | 平成22年7月1日 | 開 業 場 所 | 札幌市西区西野3条2丁目2-18 | 卒業年月日 | 平成16年3月卒 | 出 身 校 | 北海道柔道整復専門学校 |

杉浦 順平
(札幌ブロック)
<<はじめに>>
寝違いとは、あるきっかけによって頸部の運動が制限された状態である。長時間、不自然な姿勢によって筋肉が持続的に過度に収縮した状態と考えられる。その為、筋肉内に代謝産物が停滞し炎症を起こした状態であると考えられる。罹患筋としては肩甲挙筋、斜角筋が原因となる事が多いと思われる。
<<方法>>
私は炎症そのものよりも(炎症に対する冷却、消炎の処置はする)炎症を起こしやすくなってしまっている原因に対して処置を行っている。それは患者の元々の姿勢、生理的彎曲の変化などにより肩甲挙筋に高い負荷をなるべくかけない様にする事により、より早い炎症の除去、可動域制限の改善を目的に施術を行う。
当院では来院時、正面、側面からの姿勢チェック、ROMにより原因筋の特定を考えます。正面からは、左右の肩の高さ、骨盤の高さ、顔の傾き、回旋などにより、どの筋を伸張させどの筋が短縮しているのかを判断する。また頬の筋肉の左右差などからは、かみ合わせや片噛みからくる慢性的な頸部から側頭部の筋緊張を探ることができる。側面からは、生理的彎曲の確認をする。
一般的に多く見られる姿位としては胸椎の後彎、頸椎の前彎の強調、それに伴う後頭骨の後方回旋、下顎の前方突出などが多く見られる。また腰椎の後彎も多く見られる姿位である。この場合腰椎の前彎をある程度意識してもらうと頸部ROMの改善がみられることがある。
その場合、腰背部の疼痛を確認し、もし疼痛が確認されれば長期的にそちらもケアしていく必要性を頭に入れておくべきと思われる。前述の特有の不良姿勢を正常化するためには、僧帽筋、頭板状筋、半棘筋、胸鎖乳突筋、斜角筋の緊張の除去が必要と考えられる。それぞれの方法を個々に述べていきます。
当院ではまず斜角筋からアプローチします。なぜなら、下顎の前方突出に関係し、その姿位により頚椎の可動域制限に強く関係していると考えるからです。まず患者姿位は側臥位(頚椎をニュートラルに保ちやすい)術者は患者当方より施術する。患側と同側の手、つまり患者右斜角筋には術者右母指でのアプローチがしやすいと思われる。基本的には最も固く感じる方向に押圧するが、同側頚椎横突起に向けての押圧がベストと思われます。深層に腕神経叢がある為、患者の反応を診ながら丁寧にほぐす。弾くようにしてしまうとどの筋でもそうですが、揉み返し様の痛みが出現するので注意します。上腕もしくは肩甲骨内側にかけての放散痛により正しいコンタクトかを確認できる。「腕まで響きますね?」などのコメントすることによりプラシーボ効果も期待できる。
次に、頭板状筋をほぐす。同様に患者側臥位、術者も同様に頭方より施術。筋付着部がC 3 〜 7 の項靭帯Th 1 〜 2 の棘突起から乳様突起、後頭骨上項線外側で頸伸展筋なので緊張が強くなると無意識に頸前屈し疼痛回避する。押圧としては後頭骨とC 2 横突起と母指で筋をしっかりとホールドする。後頭部への放散痛が出現する。流れで半棘筋をほぐす。C 4 〜Th 6 までの横突起から後頭骨に付着する。硬化すると頸部前屈位となる。乳様突起の後方に母指をカギ型にして押し込むようにしてコンタクトする。目の奥に放散痛が出現する。次に僧帽筋をほぐす。
僧帽筋も硬化すると無意識に頸部前屈位をとる。これも側臥位で行う。腹臥位だと頸部の後屈が強くなり疼痛を誘発する恐れがある為と、僧帽筋を軽く伸張させやすい為、硬結部位に施術しやすい為である。次に肩甲挙筋をほぐす。僧帽筋の深層にある為、先に僧帽筋がある程度弛緩している事が重要である。また主要な炎症筋であることが多い為、疼痛著しい場合や熱感が強い場合は手技による施術は避け微弱な電気治療を行う事もある。次に腸肋筋への施術。Th 3 〜 7 の肋骨上縁の頸腸肋筋をほぐす。やはり硬化すると頸部前屈位をとりやすい。腹臥位で施術するが、押圧により頸部伸展時痛が出現しないように注意する。側臥位での施術後ROM確認し腹臥位にした方が賢明である。
最後に頸部を牽引する。仰臥位にて術者の指でカギ型を作り後頭骨に引っ掛けるようにして10〜15秒の間欠牽引する。これも後頸部の筋弛緩を促し頸部前屈位の解消を目的としている。
<<結果・まとめ>>
今回は不良姿位の改善により、主な原因筋と思われる肩甲挙筋の恒常的なストレス軽減それに伴う周囲筋の血行促進による、炎症の早期除去を目的とした施術です。
来院者の多くが慢性的な腰背部痛も自覚していることから、生理的彎曲の変化が寝違いを引き起こす一つの要因ではないかと考えられるのではないでしょうか。